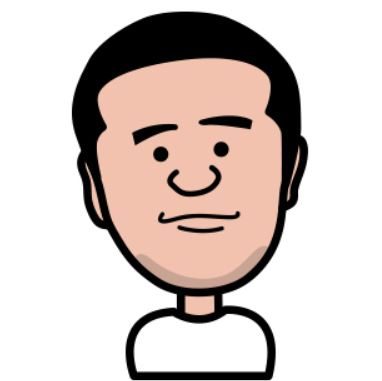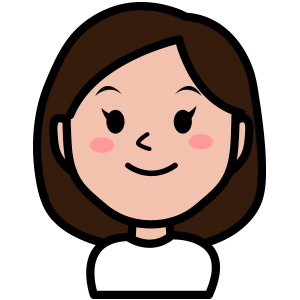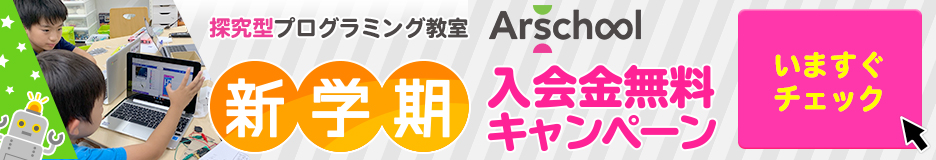変化し続ける社会で活躍するために、より一層重要視されているのが「主体性」。
2020年度に改訂された学習指導要領の中でも、「主体的・対話的で深い学び(アクティブラーニング)」がポイントのひとつになっています。


これまでの教育現場は、「学んだことを理解できているか」という知識・理解に焦点があてられがちでした。
でも、これからは「習得した知識をもとに自分で考え、表現したり判断したりできるか」ということも評価の対象となります。
参照:文部科学省公式サイト
そこで今回は、教室での体験を通して分かった、子どもの主体性を育む方法や、逆に主体性をつぶしてしまう関わり方について、紹介します。
Contents
主体性はなぜ必要?急速に変化する社会の中で生き抜こう
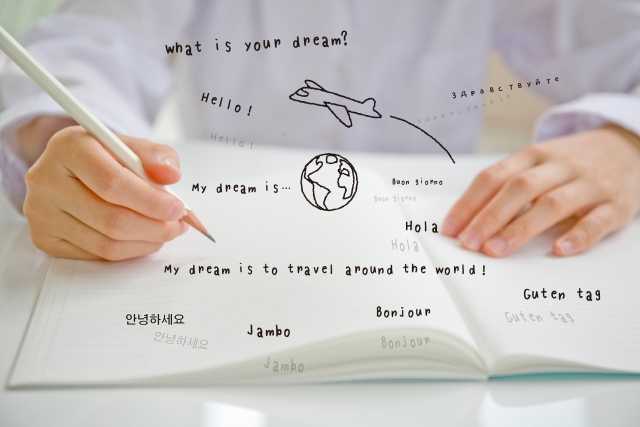
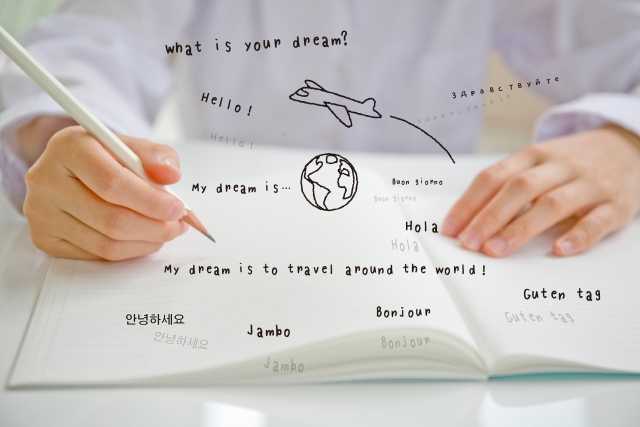
急速なIT化の影響で、10~20年後には今ある職業の49%が機械に代替される可能性があるといわれています。
さらに、グローバル化の影響で、約1/3の企業が外国人留学生を採用。
そのため、変化の激しい社会の中で子どもたちが生きぬくためには、主体性が必要です。
社会で求められている主体性とは、「自分で考え、判断し、責任をもって行動する」力。
知識・理解にとどまらず、「得た知識を生かして何ができるのか、世界や社会とどのように関わっていくのか」、という考え方までを身につける必要があります。
主体性を育む保育園や小学校


子どもの主体性を育むための取り組みを行っている保育園や小学校も多数あります。
その取り組みはさまざまですが、「子どもの興味関心を引き出す」ことを重要視している共通点があります。
興味関心から始まる活動や勉強は、子どもの探求心をくすぐり、「もっと知りたい」「こんなこともやってみたい」という主体的な学びへとつながります。
また、あらかじめ与えられたゴールをめざすのではなく、試行錯誤を繰り返しながら子どもたち自身でゴールを見つけることも大切にされています。
参照:幼児が主体的に活動できる環境の工夫 _糸満市立西崎幼稚園
主体性を育む方法|子育ての中で意識しよう


学校に任せきりにするのではなく、各家庭でも、ちょっとした工夫で子どもの主体性を育むことができます。
ここからは、子育ての中で、主体性を育む環境や接し方について解説します。
過干渉は主体性をなくしてしまう
まず、子どもの主体性を育むうえで避けたいのが「過干渉」です。
朝起きた子どもに「顔は洗った?」「早くご飯食べて」「ハンカチ持った?」と。
学校から帰宅した子どもには「手を洗った?」「おやつ出しておいたよ」「早く宿題して」と。
心配する気持ちから、つい細かく声をかけたくなるのが親心かもしれません。
ところが、親が子どもに干渉しすぎると、子どもは次第に自分で物事を考えたり、判断したりすることがなくなってきます。
「言われたものを用意しよう」「言われてからやろう」という受動的な思考に落ち着いてしまうのです。
ある程度は子どもの主体性に任せ、「学校で叱られても本人の責任」と思うことも大切です。
子どもの主体性を引き出す方法
では、どうすれば子どもの主体性を引き出せるのでしょうか?
「どうする?」と聞いて子どもに考えさせる
主体性のない子どもは、「自分で決める力」が弱い傾向にあります。
「服をどれにするか」「外食先のメニューはなにがいいか」など、ささいなことで良いので、「どうする?」と子どもに聞きましょう。
自分で決める練習を積み重ねることがポイントです。
慣れるまでは、「こっちとこっち、どっちがいい?」と選択肢を用意するのもおすすめ。
決定のハードルが低くなり、子ども自身も考えをまとめやすくなります。
自分で自分のことができるように、モノの配置を工夫する
いざ、自分で服を決めようと思っても、子どもの目の届かない場所に服があっては選べません。
このように、自分で自分のことができるようになるには、モノの配置を工夫する必要があります。
「自分で服を選べるように」「自分でおもちゃを片付けられるように」「自分でお出かけの準備ができるように」それぞれ、モノの配置を見直してみてください。
手に取りやすい、片付けやすい環境を整えることで、子どもの「やってみよう」という主体性を引き出すことができます。
自己肯定感を育てる
「自分で考え、判断し、責任をもって行動する」力である主体性。
実は、この主体性を発揮するためには自己肯定感が欠かせません。
「失敗しても大丈夫」「このままの自分を受け入れ、愛してもらえる」という自己肯定感があって初めて、「やってみよう」「挑戦してみよう」と思えるのです。
子どもの失敗を責めるのではなく、「もう一度やってみよう」「お母さんは味方だからね」という温かい見守りの姿勢を大切にしてください。
子どもの個性を受け入れる
「今日はこの服を着たい」「外遊びよりもお絵かきが好き」「辛い食べ物に挑戦したい」など、ふとした瞬間に子どもの自主性の芽が出ることがあります。
しかし、それが親の予想から外れていると「それはやめたら?」「絶対むりだよ」など、ネガティブな言葉かけをしてしまいがち。
せっかく興味をもったことを否定され続けると、子どもはやはり「言われた通りにしておこう」と思ってしまいます。
親と子どもは、血はつながっていても別の人間。
子どもの個性を受け入れ、新しいことに挑戦する機会を設けましょう。
主体性を育む遊び
主体性を育むうえで重要なのが「実体験」です。
本や動画から知識を得るだけではなく、それを活用して実際に体験するように心がけてください。
自然遊び、実験遊び、スポーツ、芸術活動など、子どもが興味をもったことにはなるべく体験させてあげたいもの。
体験の幅を広げることで、主体性を育むことはもちろん、子どもの将来の選択肢を広げることにもつながります。
次の章では、具体的な【主体性を育む取り組み】について紹介します。
キッズプログラミング教室【アルスクール】では、レッスンの中で、子どもたちの主体性を育む工夫をいくつもしています。
その方法を詳しく解説していきます。
アルスクールでの主体性を育む取り組み


子どもは主体性をみな持っています。
いたずらを含め、いろいろなことにチャレンジしたいのです。
アルスクールでは、子ども本来の主体性を大人が潰さずに発揮し伸びるように、環境をつくり、子どもと接するようにしています。
子どもの信頼を得る
「アルスクールでは否定されない、いろんなことにチャレンジできる」、そういう安心感を大切にしています。
そう子どもが心から感じないと、ダメと言われることを恐れて、子どもは自由に行動しません。
「自由にやっていいんだよ」と説明し理解してもらいつつ、何かすることを強要もせず、その子のペースに合わせてじっくり待ちます。
時には、何もしないことを認めるのも大切です。
そうすると、1,2ヶ月で子どもが変わってくることが多いです。
子どもと一緒に遊び、学ぶ
「好きに学び遊んでいい」と伝えても、やりたいことが分からない子も多いです。
「何をすればいいの?」と戸惑うケースも。
そういうときは、一緒に考え、一緒に学び遊ぶと効果的。
アルスクールでも、講師は教える立場にだけ偏るのではなく、同じ方向を向いて遊んだり、学んだりすることはよくあります。
特に小学校3年生くらいまででは、保護者の方も一緒に取り組むと劇的に変わる場合が多いです。
大人と子どもが「教える人」と「教えられる人」あるいは「監視する人」と「遊ぶ人」という関係ではなく、同じ方向を向き、一緒に行動しましょう。
発達段階や子どもの個性を見極める
例えば、10歳を超えると、大人が丁寧にやり方を説明すると「子ども扱いされたくない」と感じる子もいます。
大人よりも同級生や少し上の子どもが刺激になることも多いです。
一方で、8歳くらいだと、自分のイメージする作りたいものが、自分のスキルでは作れないことを理解し、もどかしさを感じることが多いです。
例:テレビゲームみたいなものが作りたい!
その結果、学びが止まってしまうこともあります。
そのため、アルスクールでは、子どもの発達段階や子どもの個性をよく見ながら、レッスンを進めています。
性別によっても傾向があります。
例:レゴ
- 男の子は作っては壊し、また作る
- 女の子はストーリーにそって作品を作り、それをさらに膨らます
このように、子どもの発達段階や、個人の好みをよく見ながら接することで、主体的に子どもが行動するようになります。
口頭ではなく、動作でお手本を見せる
主体性を育むといっても、子どもは発育途上であり、やりたいけどできないから嫌になることもすごく多いです。
モンテッソーリ教育では、子どもと同じ目線の高さで同じ方向を向き、口で説明せずゆっくりとお手本を見せます。
特に幼児〜小2くらいまでは言葉の説明はイメージが沸かず、また説明と動作を同時に理解できません。
子どもができるようになる工夫をしていきましょう。
成長を急がず、プロセスを評価する
大人はつい「子どもが何かできるようになること」を評価し子どもと接してしまいがちです。
暗に成果を求められるような中では、やる気を失う子が多いです。
(成果を出すことがモチベーションになる子もいるので、子どもの個性によります)
目に見える成果以外にも子どもは成長しています。
1つの作品を作るにしても、試行錯誤して何パターンも試した結果であれば、10個、20個作るのと同じくらい学べている場合もあります。
大人からすると、「何それ?」と感じるものを作ったとしても、「どのように考えて、どうやって作ったのか」のプロセスを聞いてあげてほめると、子どもの成長につながります。
そのため、アルスクールでも、作り上げた作品をみんなの前でフィードバックすることを大切にしています。
できたものだけでなくその過程も理解して、自己肯定感を養うようなコミュニケーションを取りましょう。
主体性の育て方まとめ


主体性を伸ばすための環境づくりは、言葉で書くと難しく感じるかもしれません。
でもストレスを抱えてまで全部を揃える必要ありません。
一番大切なのは「子どもを信頼し、コミュニケーションを取り、成長を急がない」ことです。
それさえできれば大丈夫。
保護者と子どもが信頼しあえているご家庭は、どこかで必ず子どもが伸びます。
多くの保護者の方から「分かってはいるんですけど、ついキツくいってしまう」と聞きます。
子どものことを思う保護者の方はそういうものです。
余り気にせず、子どもとの時間を楽しみましょう。
とはいえ、ご家庭だけではなかなか難しく息が詰まることもあるでしょう。
キッズプログラミング教室【アルスクール】では、子どもたちが伸び伸びと主体的に活動しています。


ゲーム作成や工作とプログラミングを組み合わせた創作などを通して、楽しくレッスンを行っています。


また、一人ひとりの発達段階や興味によって、教材やレッスンの進み方を調整しています。
ぜひ一度遊びにきてみてください。


キッズプログラミング教室【アルスクール】では、オンラインで学べるプログラミングレッスンを行っています。
冬の入会金無料キャンページ実施中!通常11,000円する入会金が、今だけ0円です。
実際のレッスンに参加できる無料体験で、この機会にアルスクールの学びを体験してみませんか。
また、実際の教室でもレッスンを行っています。
- 東京にお住まいの方 → 自由が丘校、中野校
- 大阪にお住まいの方 → 大阪南千里校
- 福岡にお住まいの方 → 福岡西新校
教室での無料体験レッスンをご希望の方は、こちらをご覧ください。